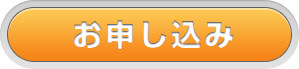| 第1・3金曜日 13:30~15:00 4月18日~6月20日 全6回 〔4/18、5/2・16・30、6/6・20〕 ※5月は第1・3・5金曜 |
 | 武田 比呂男(十文字学園女子大学名誉教授、明治大学兼任講師) |
 | 日本最古の歌集『万葉集』のなかで、作られた時期が明らかなうたは新旧で130年ほどの開きがあります。それは天皇を中心とした統一国家が成立していく時期や、律令制国家が衰退を始める時期など、激動の時代を含みます。作者たちの多くが古代の歴史のなかでさまざまに活躍する、天皇とその一族や、古代豪族の末裔氏族に、新進の貴族官僚たちです。『万葉集』のなかに歴史があるのです。古代の歴史を見据えながら読むことで『万葉集』の新たな魅力が発見できるでしょう。 今期は、大伴家持が越中国の国守として赴任して間もない時期、天平19年(747)の歌を中心にみていきます。弟書持の死から立ち直る間もなく、自身が死を意識するほどの病を得た家持は、回復後は都の妻を思い、また近畿周辺とは異なる風土との出会いを歌います。古代史や『万葉集』に関するミニ知識満載の講座です。『万葉集』を通じて古代の人々の息吹を感じてみませんか。 ※万葉集を継続して読んでいますが、各回独立した内容ですので、途中からの参加も大歓迎です。 ★カリキュラム 第1回 「未だ山柿の門に逕ず」(更に贈る歌)/巻17・3969~3972 第2回 大伴池主・天平十九年晩春の歌/巻17・3973~3975 第3回 都の妻を想う(恋緒を述ぶる歌)/巻17・3978~3982 第4回 立夏を過ぎても鳴かないホトトギスを恨む/巻17・3983~4 第5回 二上山の賦(越中三賦1)/巻17・3985~3987 第6回 布勢の水海に遊覧する賦(越中三賦2)/巻17・3991~2 ★講師プロフィール 日本古代文学、民俗文化専攻。著書に『仏法と怪異 日本霊異記の世界』、共著書に『躍動する日本神話』、『シャーマニズムの文化学』、論文に「大伴家持の祈雨歌小考」、「流離する貴種の論理ー折口信夫論の試みー」など。 |
 | 21,120円(税込・6回分) ※別途、設備使用料990円(税込・6回分)がかかります。 |
 | ◆資料代 660円(税込・6回分) |